「輸入車の関税って結局、誰が誰に払うの?」
海外から車を買おうとした時に、
まずつまずきやすいのがこの疑問です。
関税込み表示に安心していたら、
後から高額な税金を請求された…
そんなトラブルも少なくありません。
関税の基本的な仕組みから、
個人輸入と業者依頼の違い、
国別の関税率や免税の特例まで、
実例や数字を交えて丁寧に解説しています。
初めての方でも、輸入車購入に必要な費用と
流れがしっかり理解できる内容です。
- 輸入車の関税、誰が払う?基本の仕組みを徹底解説
- 輸入方法によって変わる!個人輸入 vs 業者輸入の関税の流れ
- 国別で違う!アメリカ・ドイツ・イギリスからの車の関税率一覧(2025年版)
- 新車と中古車で違う?車の種類別・関税のかかり方
- 購入価格以外に必要な費用とは?関税以外の税金・手数料まとめ
- 実例で解説!eBayモータースやカーセンサーで購入した際の税金の流れ
- 関税はどこでどうやって支払う?支払い方法・場所・タイミング完全ガイド
- 関税が免除される場合とは?知っておきたい特例と条件
- 自力輸入 vs 業者依頼:トータルコストでどちらがお得?徹底比較
- 関税申告のために必要な書類一覧と書き方のポイント
- 車を日本に持ち込んだ後の登録・ナンバー取得の流れ
- 中古車輸入でかかる「隠れコスト」排ガス規制・車検対応の費用
- この記事のまとめ
輸入車の関税、誰が払う?基本の仕組みを徹底解説

海外から車を輸入する際・・・
「関税は誰が払うのか?」というのは
最初につまずきやすい疑問の一つです。
これは・・・
個人輸入か?業者経由か?によって異なります。
また、「関税込み」と書かれた
車両価格にも注意が必要です。
ここでは、関税の基本的な仕組みと
支払者のルールをわかりやすく解説します。
関税は「購入者」or「販売者」?支払い義務のあるのは誰?
結論から言うと・・・
原則として関税を支払うのは「輸入者」=車を日本に持ち込む人です。
つまり、あなたが個人で海外から車を輸入する場合は・・・
あなた自身が関税の支払者になります。
ただし、業者や輸入代行サービスを
利用した場合は少し変わります。
多くのケースでは、以下の2パターンがあります。
- 輸入業者が輸入者として通関し、関税を支払うケース:この場合、見積書に「関税・消費税込み」と明記されていれば、実際の支払いは業者が行い、料金に含まれています。
- 輸入者が自分の名前で通関をするケース(個人輸入):この場合は、輸入時に税関から直接請求されます。
関税を誰が払うかは「輸入者は誰か?」で決まる。
支払いの実務を誰が代行するかとは別の話!
「関税込み」とは本当?誤解しやすい表記の落とし穴
「関税込み」と記載された車両価格を見て
安心していませんか?
実はその表記にはいくつかの落とし穴があります。
たとえば・・・
- アメリカやドイツの中古車販売サイトで「Price includes import duties」と書かれていても、それはその国の輸出に関する費用込みであり、日本側の関税は別途発生するケースもあります。
- 日本国内の業者サイトで「関税込み」表示がある場合でも、車両本体価格にしか含まれておらず、輸送費・登録費・消費税は別途というケースも。
- 「関税込み」と書かれている場合、日本の関税か、輸出国の費用かをしっかり確認する。
- 「総額表示」でない場合、港に着いてからの支払い(関税+消費税)が発生することがある。
- 心配な場合は、業者に「関税・消費税・輸送費は総額に含まれていますか?」と確認を!
輸入方法によって変わる!個人輸入 vs 業者輸入の関税の流れ

車を海外から輸入する場合・・・
「自分でやる個人輸入」と
「業者に任せる輸入代行」では、
関税の支払い方法やタイミング、
さらには全体の流れが大きく異なります。
どちらを選ぶかによって、手間やコスト、
トラブルのリスクが変わってくるので、ここでは・・・
それぞれの輸入方法の具体的な
流れやポイントを解説していきます。
個人輸入の場合:支払いタイミングと手続きの全体像
まず、個人輸入とは・・・
「あなた自身が輸入者として、
海外から直接車を購入・通関する方法」
です。
たとえば・・・
アメリカの中古車販売サイト「eBay Motors」で
日産の350Zを見つけて、個人で購入するケースを
想像してみてください。
この場合、以下のような流れになります。
- 現地サイトで車両を購入・支払い(USDなどで)
- 現地から日本までの海上輸送手配(船会社 or 輸送代行)
- 日本到着後、税関で通関手続き(インボイス・B/Lなど提出)
- この時点で関税・消費税を支払う(港でor事前に銀行払い)
- 通関完了後、ナンバー取得のための検査・登録手続きへ
個人輸入でよくある関税の支払いタイミングは、
税関の通関手続き時です。通関士を使わず、
自分で申告する場合は・・・
書類の準備(車両インボイス・B/L・
譲渡証明書など)がかなり重要になります。
たとえば・・・
アメリカから総額300万円の車を輸入した場合、
関税が約10%、消費税10%が加算されます。
つまり、ざっくり・・・
関税30万円+消費税33万円=合計約63万円
が追加で必要になることも。
また、港によっては・・・
「現金払いのみ」
「カード不可」
「事前の銀行振込のみ対応」
など支払い方法が限定されていることもあるので、
事前確認は必須です。
業者輸入の場合:代行費用や注意点も含めて解説
次に、業者輸入の場合です。
これは、輸入代行業者や専門ディーラーが
あなたの代わりに車の購入から輸送、
通関までをすべて代行してくれるスタイルです。
たとえば、「オートモール」や
「ファストレーンジャパン」といった業者では、
「ドイツからBMWを関税込み・車検取得込みで納車」
といったパッケージサービスを提供しています。
- 業者に希望車種・予算を伝えて見積もり依頼
- 業者が現地で購入し、日本へ輸送
- 業者が輸入者として通関・関税・消費税を支払い
- 車検・登録まで対応し、自宅や指定ディーラーで納車
このように、関税は・・・
業者が一旦支払い、
それを「関税込み価格」としてあなたに請求する
パターンが一般的です。
たとえば、車両価格が200万円でも、
関税+消費税+代行費+検査・登録費などを含めると、
最終的に250~280万円程度になることも珍しくありません。
また「関税込み」と表示されていても、
「消費税や登録費用は別途」のケースがあるので、
総額表示されているかどうかを必ず確認しましょう。
どちらを選ぶにしても・・・
「時間をかけてでもコストを抑えたい人」は個人輸入向き。
「手間を省いてリスクも避けたい人」は業者輸入向きです。
それぞれの特徴を理解した上で、
自分に合った方法を選ぶのがポイントです。
国別で違う!アメリカ・ドイツ・イギリスからの車の関税率一覧(2025年版)

車を海外から輸入する際・・・
関税率は輸入元の国によって異なるというのは
意外と見落とされがちです。
「どこから輸入するか」で、
最終的なコストが大きく変わってきます。
ここでは、輸入ニーズの多い・・・
アメリカ・ドイツ・イギリスの最新の
関税事情(2025年時点)を、
実際の計算例も交えて解説します。
これを知っておくことで・・・
「思ったより高くついた…」
という失敗を防げます。
アメリカ車:乗用車の関税は約10%!具体的な計算例付き
アメリカから車を輸入する場合、
日本では乗用車に対して約10%の関税が課せられます。
(トラックや商用車の場合はさらに異なる率になるので要注意です!)
たとえば、アメリカの中古車オークションサイトで
フォード・マスタング(購入価格:2万ドル)
を見つけて輸入すると仮定しましょう。
- 車両価格:20,000ドル(約300万円)
- 海上輸送費:2,000ドル(約30万円)
- 輸送保険:500ドル(約7.5万円)
→ CIF合計:約337.5万円
このCIF価格に対して、
- 関税(約10%):約33.7万円
- 消費税(10%):関税込みの価格に対して→約37.1万円
という形で課税されます。つまり・・・
関税+消費税だけで約70万円近い税金が追加で必要になる。
ということになります。
なお、アメリカ車の輸入には・・・
「排ガス検査」や「車検対応」の追加費用もあるため、
全体でプラス100万円前後の
コスト増は見込んでおくと安心です。
ドイツ車・EU圏:EPA協定による関税免除の条件とは
一方で、ドイツをはじめとする
EU諸国からの車の輸入には、大きなメリットがあります。
それが、日EU経済連携協定(EPA)による
「関税の免除措置」です。
このEPAにより、一定の条件を満たしたEU製品(自動車を含む)に
ついては、関税がゼロ%になる可能性があります。
- 車両がEU域内で完全に生産されたこと(原産地証明書が必要)
- 「EPA適用希望」と通関書類に明記されていること
- 原産地証明書(様式AやRCEP対応書類など)が正しく提出されていること
たとえば、ドイツのディーラーからBMW 3シリーズ(CIF価格:約400万円)を輸入する場合、本来なら約40万円の関税が発生するはずですが、原産地証明がしっかり出ていれば関税は0円になります。
ただし、書類に不備があると通常の関税(約10%)が課せられるため注意が必要です。「EPAがあるから大丈夫」と油断せず、事前にディーラーや業者としっかり確認しておくことが大切です。
なお、イギリスは2021年にEUを離脱しましたが、**日英EPA(経済連携協定)**が別途締結されています。こちらもドイツと同様に、原産地証明があれば関税は基本的に免除されます。
まとめると…
- アメリカ車 → 原則関税10%+消費税10%、書類も複雑
- ドイツ・EU車 → 条件を満たせば関税0%、ただし証明書が重要
- 関税の違いだけで数十万円単位の差が出るため、輸入先選びは慎重に!
新車と中古車で違う?車の種類別・関税のかかり方
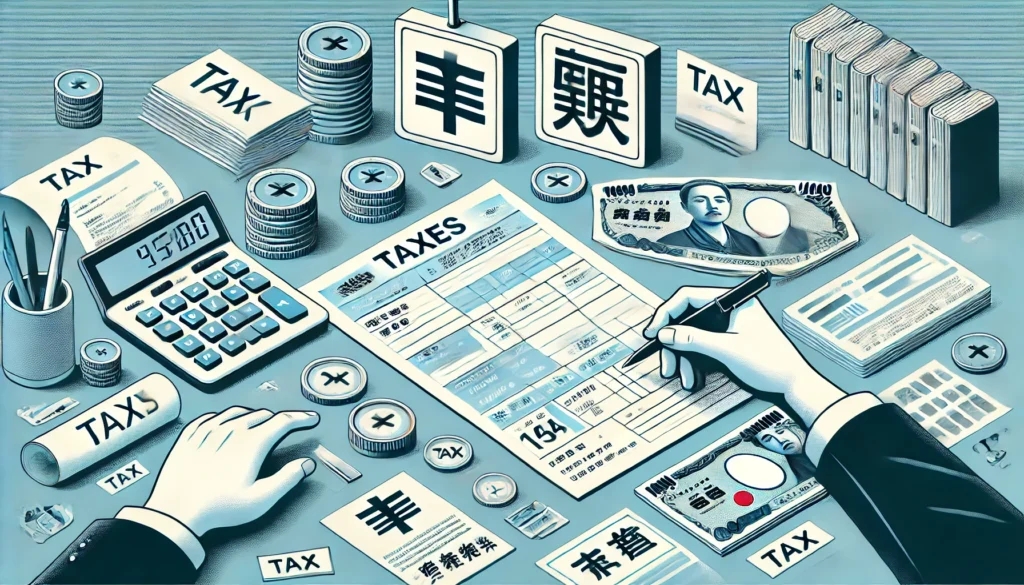
車を海外から輸入する際・・・
「新車と中古車で関税の額に違いはあるの?」と
疑問に感じる方は多いと思います。
実は、関税率自体は新車・中古車に関係なく
同じ率が適用されるのが基本です。
ただし、車の年式や排気量、環境性能によっては、
別の費用や条件が追加で発生することがあるため注意が必要です。
ここでは・・・
「中古車」「電気自動車(EV)」といった車種別に、
どんな税負担や優遇措置があるのかをわかりやすく解説します。
中古車にも関税はかかる?年式・排気量で変わる税負担
まず結論から言うと・・・
中古車であっても関税はしっかりかかります。
新車と同じように・・・
CIF価格(=車両価格+輸送費+保険料)を基準に、
約10%の関税が課税されるのが一般的です。
ただし、中古車ならではの注意点があります。
それが「年式」と「排気量」です。
たとえばアメリカから・・・
2008年式のトヨタ・ハイランダー(排気量3.5L)を
輸入するケースを想定してみましょう。
- 関税(10%):約25万円
- 消費税(10%):約27.5万円
→ 合計:約52.5万円の税金が発生します。
ここに加えて、中古車の場合は以下のような
追加のコストがかかる可能性があります。
- 排気ガス検査費用(年式が古いほど規制に適合しづらい)
- 消音・照明などの改修費(日本の保安基準に合わせる必要がある)
- 車検対応のための整備費用
特に10年以上前の車や大排気量の車は・・・
環境規制に適合させるために数十万円の
改造費が必要になることもあります。
「安く買ったつもりが、日本での登録に想定外の費用がかかった…」
という失敗例も少なくないので、
購入前にしっかりチェックしましょう。
電気自動車(EV)は優遇される?環境規制との関係性
最近人気が高まっているEV(電気自動車)ですが、
関税や各種税金の面では、一部優遇される傾向があります。
まず、EVであっても・・・
関税の基本率(約10%)は変わりません。
ただし、日本ではEVに対して
以下のような、間接的な優遇措置が存在しています。
- 自動車取得税の免税(または軽減)
- 環境性能割の非課税対象
- 一部地域での補助金制度あり(例:東京都のZEV補助金など)
たとえば、アメリカから・・・
テスラ・モデル3(CIF価格:500万円)を輸入した場合、
関税は約50万円、消費税は約55万円になりますが、
国内での登録時に取得税や環境性能割が、
「0円」になる可能性があります。
また、EVは排ガス規制の対象外なので、
ガソリン車のような「排気ガス試験」や
「消音対応」といった・・・
面倒な技術基準の調整が不要になることが多く、
その分手間と費用が抑えられるのもメリットです。
ただし、注意点としては・・・
充電設備の設置やパーツ交換の難しさ(特に右ハンドル仕様)など、
日本での使用にあたって独自の課題もあるため、
輸入する際には事前にメンテナンス体制も確認しておくと安心です。
まとめると…
- 中古車も新車と同じく関税は約10%、ただし年式や排気量によっては別のコストが増える
- EVは関税は変わらないが、排ガス対応不要&国内税制面で優遇あり
- 総コストは「関税+消費税+整備費用+補助金」まで含めて試算するのが大切
購入価格以外に必要な費用とは?関税以外の税金・手数料まとめ

海外から車を輸入する場合・・・
「車両本体の価格だけを見て購入を決めてしまった・・・」
という方が意外と多いです。
ですが実際には・・・
関税・消費税・登録関連の手数料・検査費用など、
さまざまな費用が上乗せされるため、
トータルで考えないと「思ったより高くついた…」という
失敗にもなりかねません。
関税以外でかかる代表的な税金や手数料の内容・
計算方法・支払いのタイミングまで、
ひとつひとつ丁寧に解説していきます。
関税・消費税・自動車取得税の計算方法と発生タイミング
まずは代表的な「関税」「消費税」「自動車取得税」の3つについて、それぞれの計算方法といつ発生するのかを見ていきましょう。
- 発生タイミング:日本に車が到着して通関手続きを行うとき
- 税率の目安:乗用車は原則約10%
- 計算式:
CIF価格 × 10%
(CIFについては次の項目で解説します)
たとえばCIF価格が300万円の車であれば、
関税は約30万円となります。
- 発生タイミング:関税と同じく通関時
- 税率:10%
- 計算式:
(CIF価格 + 関税)× 10%
例)CIF 300万円+関税30万円=330万円 → 消費税:33万円
関税の上にさらに課税される・・・
「二重課税」的な構造になっている点が、
見落としやすいポイントです。
- 発生タイミング:車を登録する時(=ナンバーを取得する時)
- 税率:車の環境性能に応じて0~3%程度(EVなら0%が多い)
たとえば・・・
環境性能がそれほど高くないガソリン車を輸入した場合、
車両価格300万円に対して約2%の環境性能割が
かかるとすれば、6万円程度の支払いが必要になります。
この他にも・・・
「重量税」や「自賠責保険料」「検査手数料」なども
別途発生しますが、まずは・・・
この3つが最も大きな税金になります。
CIF価格とは?保険・送料込み価格に関税はどう加算されるか?
関税や消費税を計算するうえで基本になるのが・・・
CIF価格(シーアイエフ価格)です。
これは、以下の3つを合計したもの!
- Cost(車両価格)
- Insurance(海上保険)
- Freight(輸送費)
つまり、単純な車両の購入価格だけではなく、
日本に届くまでの“輸送に関わる全費用”を
含めた価格が「課税のベース」になります。
- 車両本体価格:2万ドル(約300万円)
- 輸送費(F):2,000ドル(約30万円)
- 海上保険(I):500ドル(約7.5万円)
→ CIF価格:337.5万円
これに対して・・・
- 関税(10%):約33.75万円
- 消費税(10%):(337.5万+33.75万)× 10% = 約37.1万円
→ 関税+消費税だけで約70万円強
このように、「たった2万ドルの車なのに、
70万円以上の税金がかかる」というのは、
CIF価格がベースになるからなんですね。
- 輸送保険や海上運賃が高額なケース(大型車・長距離)は、CIFが高くなり課税額も上がる
- CIF価格の内訳は、インボイス(請求書)に明記されている必要があります
- 日本側での通関時に「CIFが不明瞭」と判断されると、税関が独自の査定価格で課税することもあるため、正確な書類準備が重要です
まとめると…
- 関税:約10%、消費税:関税込みに10%、自動車取得税:約0~3%
- 計算はCIF価格をベースにされる
- CIFの中には保険や輸送費も含まれるため、予想以上に課税額が増えるケースも
「なんとなく輸入費用が高い」と感じていた理由は、
実はこの“CIF基準の多重課税構造”にあるんです。
だからこそ、購入前に正確な総額シミュレーションを
しておくことが失敗しないコツです。
実例で解説!eBayモータースやカーセンサーで購入した際の税金の流れ

最近では、アメリカの「eBay Motors」や、
日本でも並行輸入車が多く掲載されている
「カーセンサー」などのサイトを使って、
海外の車を個人で購入する方も増えてきています。
でも、「買って終わり」ではなく、
そこから始まる税金・通関・登録といった
手続きが意外と複雑なんですよね。
ここでは、eBayなどの海外サイト、
あるいは国内サイトで輸入車を買った際の
実際の流れと注意点を、税金面を中心に
具体的に解説していきます。
購入から納車までに必要な費用と手続きの流れ
まずは、アメリカのeBay Motorsで車を買ったケースで見ていきましょう。
- eBayでの落札価格:20,000ドル(約300万円)
- 海上輸送費:2,000ドル(約30万円)
- 輸送保険料:500ドル(約7.5万円)
→ CIF価格合計:約337.5万円
ここから日本で発生する主な手続きと
費用は以下のとおりです。
- 関税(10%):約33.75万円
- 消費税(10%):(CIF+関税)×10% ≒ 約37万円
- 通関代行手数料:約1~3万円(通関業者を使う場合)
→ 通関時の支払合計:約70万~75万円
- 予備検査(排ガス・光軸・速度など):5万~15万円
- 自動車取得税(環境性能割):CIF価格の1~3%、今回は約7万円前後
- 自賠責保険・重量税・印紙代など登録関連費:約5万~10万円
- ナンバー取得代行・名義変更手数料:約1~3万円(代行依頼時)
→ 登録時の支払合計:約20万~30万円
- 右ハンドル仕様へのパーツ交換(必要に応じて):10万~20万円
- 車検整備・消耗品交換費用:5万~15万円
車両価格300万円+輸送関連費用約37.5万円+税金・登録費用約100万円 →
総額:440万~470万円前後になるケースも
ちなみに、カーセンサーなどの日本のサイトで
「並行輸入車」を購入した場合は、すでに国内に
到着済みのことが多く、関税や消費税は販売業者が
支払済みになっています。
ただし、「関税込み」と書かれていても、
消費税や登録費用が別途発生することも多いので、
見積もりの詳細をしっかり確認しておくことが大切です。
支払いトラブルや関税未納のリスク事例
「車を買ったはいいけど、税金や通関で大トラブルになった…」
という事例も少なくありません。ここでは・・・
よくある失敗パターンやリスクを紹介します。
eBayで車を買って「日本に届いたらすぐ乗れる!」と思っていたが、港で関税の請求を受けてびっくり。しかも、支払いに現金が必要で、クレジットカードが使えなかったという例も。事前に支払い方法を確認していないと、車が港に“足止め”されてしまいます。
インボイス(請求書)に「車両本体のみ」の価格しか書いておらず、税関から「CIF不明」と判断され、税関側で独自に高めのCIFを設定→過剰な課税になったというトラブルも。輸送費や保険料を明記したインボイスを用意するのが大事です。
国内の並行輸入業者で「コミコミ価格だと思って契約したのに、あとから関税分が別請求された」というケース。「総額表示」か「関税・消費税込み価格」かをはっきり確認しておかないと、あとでトラブルになることがあります。
- インボイスやB/L(船荷証券)などの書類をきちんと揃える
- 通関・登録までをカバーしてくれる信頼できる代行業者に依頼する
- 「税込み」「諸費用込み」などの表記はどこまで含まれているのかを明確に確認する
ここまでのまとめ!
- 海外サイトで買った場合、関税・消費税・登録費用で100万円以上追加されることも
- トラブル防止には「正確な書類」と「費用明細の確認」が必須
- 初めて輸入するなら、実績のある輸入代行業者を使うのが安全
関税はどこでどうやって支払う?支払い方法・場所・タイミング完全ガイド
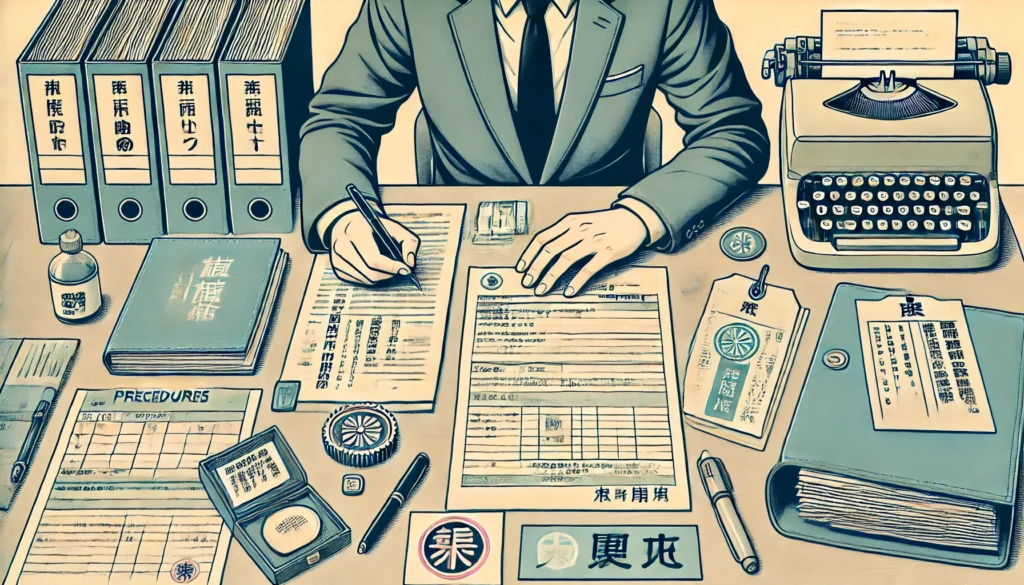
輸入車の購入では・・・
「関税がかかる」
ということは知っていても、実際にいつ、
どこで、どんな方法で支払うのか?
など、そこまでは・・・
あまり詳しく知られていないポイントです。
特に初めて個人輸入をされる方にとっては、
ここが不安のタネになりやすいんですよね。
ここでは・・・
関税の支払い方法と場所、
さらに業者に頼んだ場合のコストや注意点まで
具体例を交えながら詳しく解説していきます。
港・空港での支払い方法:現金、銀行振込、クレジットは使える?
まず、個人で車を輸入する場合・・・
関税の支払いは、通関手続きのタイミングで行います。
つまり、車が日本に到着して、税関に申告・
審査を受ける際に、関税と消費税を支払わないと
車を引き取ることができません。
支払いの場所とタイミング
- 支払いは基本的に、車が到着した港や空港(成田・羽田・横浜港・名古屋港など)での通関時
- 税関の指定する支払い窓口、または指定銀行口座への振込になります
支払い方法にはいくつか種類がありますが、注意が必要です!
| 支払い方法 | 対応可否 | 備考 |
| 現金 | ◯(可能) | ただし高額だと持参リスクあり/一部港では非推奨 |
| 銀行振込 | ◎(推奨) | 通関業者・税関指定の口座に振込。多くの人がこの方法 |
| クレジットカード | △(原則不可) | 一部の港で例外的に対応しているが、基本は非対応 |
たとえば、横浜港の場合は・・・
支払い用紙に記載された「納付番号」を使って、
みずほ銀行などの指定口座へ事前に
振り込みをする形式が一般的です。
また、支払う金額が50万円を超えるケースも多いため、
現金での持参はリスクが高いですし、
その場でクレジットカード決済ができない
ことも多いので、事前に準備をしておく必要があります。
ちなみに、港での関税支払いと同時に消費税も
一緒に払いますので・・・
CIF価格+関税を合計した額の10%
が、一気に乗ってくる形になります。
業者に代行依頼した場合の追加コストや注意点
一方で、通関手続きや関税支払いを
輸入代行業者や通関業者に任せるという
選択肢もあります。
特に初めての方や時間が取れない方には、
非常に助かるサービスです。
- 関税や消費税の支払いを代行してもらえる
- インボイスやB/Lなどの書類不備によるトラブルを未然に防げる
- 書類提出・申告・受け取りまで一括対応してもらえる
- 代行費用が上乗せされる
→ 相場としては1万円~3万円前後が多いですが、大手業者やフルサポートプランになると5万円以上になることも。 - 「関税別」表示に注意
→ 車両価格が安く見えるように「関税・消費税は別途」と書かれていることがあります。総額表示かどうかを確認するのが必須です。 - 業者に全て任せきりにすると、内訳が不明瞭になることも
→ 例えば「コミコミ400万円」と言われても、その中に関税がいくら含まれているかが分からないと、比較検討がしにくくなります。
たとえば…
ドイツからBMWを並行輸入してくれるA社では、「車両本体価格:380万円(関税込)+代行手数料:3万円」という明朗な提示がある一方で、B社では「車両価格:350万円(関税別)」と安く見える表示で、最終的には関税・消費税・登録費用などが追加されて合計420万円を超えるという事例もあります。
ここまでのまとめ
- 関税は、日本の港や空港で通関時に支払い。現金か銀行振込が主流で、クレカは基本NG
- 安心したいなら業者に支払い代行を依頼するのも手。ただし、代行費用や「総額表示かどうか」は必ず確認
- 支払いトラブルを避けるためには、通関時の段取りと書類の整備がカギ
関税が免除される場合とは?知っておきたい特例と条件
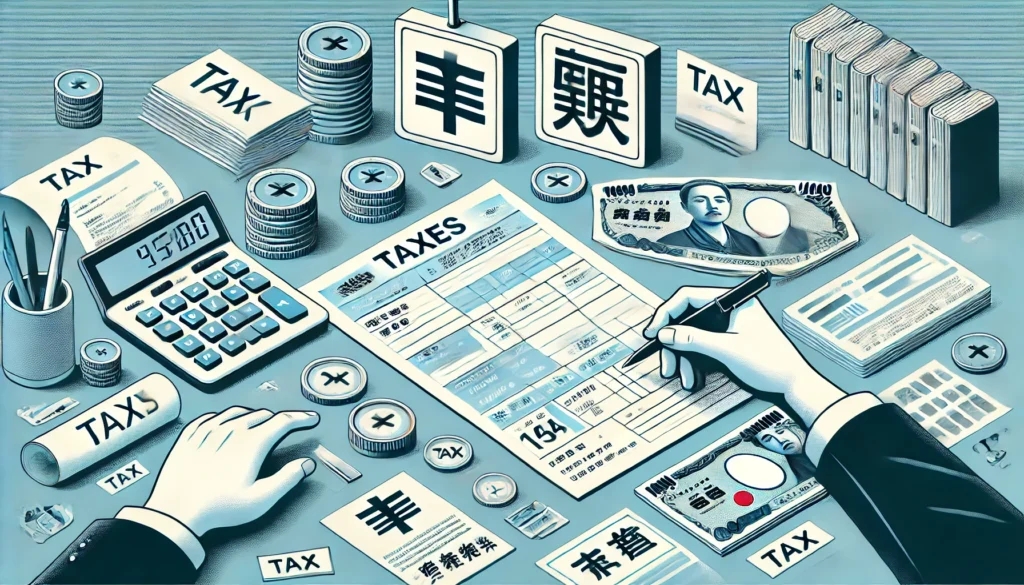
輸入車には原則として関税がかかりますが、
実はすべてのケースで関税が課税されるわけではありません。
条件を満たすことで、関税が免除される特例制度が
いくつか存在します。
こうした制度をうまく活用できれば、
数十万円単位の節約になることもあります。
ここでは、主に「年式による免税措置」や
「生活用財としての免税輸入」など、
代表的な関税免除のケースについて詳しく解説していきます。
一定年数経過車の免税措置とは?
まずよく話題になるのが・・・
「古い車は関税がかからない」といった噂です。
これ、半分正解で、半分誤解なんです。
結論からいうと・・・
一定の条件を満たした中古車(クラシックカー扱い)については、
関税が免除になる可能性があります。
これは「アンティーク自動車(ヴィンテージカー)」
という扱いになるためです。
- 製造から20年以上経過している
- 文化的・歴史的価値が認められる(完全オリジナル、希少モデルなど)
- 修復・改造が最小限である(カスタム車は対象外になることが多い)
たとえば…
1990年代のポルシェ911やフェラーリF355など、製造から30年以上経過し、外装・内装ともにオリジナルパーツで維持されている個体であれば、「美術品」や「収集品」としての通関申告が通るケースもあります。
この場合、関税が免除されるだけでなく、場合によっては消費税も軽減されることもあります。
ただし、審査は厳しく、税関での個別判断となるため、
事前に輸入通関の専門業者と相談し、
証明書類(製造証明、写真、鑑定書など)を
しっかり準備しておくことが重要です。
移住や転勤に伴う「免税輸入」のケースも紹介
次に、「生活用財としての免税輸入」という制度もあります。
これは、海外から帰国・転勤してきた人が、
海外で使っていた自家用車を日本に持ち込む場合に限り、
関税・消費税が免除されるというものです。
- 日本への入国日から6か月以内に申告・輸入すること
- 輸入する車を6か月以上、海外で自己所有・使用していたこと
- 個人的使用目的であり、輸入後1年間は転売・譲渡しないこと
- 「別送品」として届け出ておく必要がある(空輸・船便ともに可)
たとえば…
ドイツに5年間駐在していた方が、BMWを所有していて、日本帰国時に持ち帰るケース。
この場合、「別送品申告書」を空港の税関で提出し、車を船便で送れば、関税・消費税ともに0円で通関できる可能性があります。
- 購入したばかりの車(帰国直前に買った車)は対象外
- 家族名義や会社名義の車も、自己使用の証明が取れなければNG
- 日本到着後、すぐに売却すると「税逃れ」として追徴課税の可能性も
この制度は・・・
「生活の延長」として自分の持ち物を持ち帰る
という考え方が前提になっています。
正しく使えば非常にありがたい制度ですが、
誤った運用はリスクを伴いますので、
事前に税関の窓口や通関業者に確認を取るのが安心です。
ここまでのまとめ!
- クラシックカー(20年以上)などは、条件次第で関税免除の可能性あり
- 海外からの帰国・転勤時の「別送品免税」制度を活用すれば、関税・消費税ゼロも可能
- いずれも、事前申請・証明書類の準備・使用履歴の確認が必須
このように、ちょっとした知識と準備で、
数十万円単位の節税ができる可能性もあります。
自力輸入 vs 業者依頼:トータルコストでどちらがお得?徹底比較

「輸入車って個人で直接買った方が安いんじゃない?」
そう思って調べ始める方は多いですが、
実は“安さだけ”で判断すると後悔することも多いんです。
ここでは・・・
自力輸入と業者依頼、それぞれのコスト・
手間・リスクのバランスを徹底比較しながら、
「結局どっちが自分にとって最適なのか?」
という視点で解説していきます。
手間・費用・リスクのバランスで考える最適な選択肢
まずは、両者の違いを・・・
簡単にまとめてみましょう。
| 比較項目 | 自力輸入 | 業者依頼 |
| 車両本体価格 | 安く買える(中間マージンなし) | やや割高(手数料含む) |
| 関税・消費税 | 自分で計算・支払い | 業者が代行してくれる |
| 通関手続き | 自分で準備・申告が必要 | 全部お任せ可能 |
| 書類の整備 | 要知識・英語読解も必要 | 業者が確認・翻訳してくれる |
| リスク対応 | 自己責任(遅延・トラブル) | 保険対応・業者保証あり |
| トータルコスト | 安く済む可能性あり(※手間大) | 割高でも安心・時短効果大 |
たとえば実際の比較例
- 車両価格:約300万円
- 輸送費+保険:約37.5万円
- 関税・消費税:約70万円
- 登録・検査など:約30万円
→ 合計:約440万円前後(書類・通関は自力対応)
車両+輸送+関税+登録+整備込パッケージ:約480万~500万円
→ 代行手数料・サポート料:+40~60万円前後
差額だけ見ると、確かに・・・
自力輸入の方が30~50万円ほど安い計算になりますが、
そこには以下のような見えにくいコストも含まれています。
- 税関とのやりとりにかかる時間とストレス
- 不備による車両引き取りの遅延リスク
- 排ガス試験や検査不合格による追加整備費用
- 英語の見積書・契約書の誤読によるトラブル
「時間が取れて、手続きが得意、
リスクも自己責任でOKな方」には・・・
自力輸入が向いていますし、
「失敗したくない・手間をかけたくない・
少し高くても確実がいい」という方には、
業者依頼が断然おすすめです。
人気の輸入代行業者とその料金体系(例:オートモール、ファストレーンなど)
それでは実際に、国内で人気のある
輸入代行業者をいくつかご紹介します。
料金体系やサービス内容を把握しておくと、
比較もしやすくなります。
- 主にアメリカ・ドイツ車に強い業者。独自の現地ネットワークで良質な在庫を確保
- 料金体系:
- 代行手数料:15万円~30万円程度(車両価格により変動)
- 関税・消費税:含む or 別途選択可能
- 納車整備・登録までのパッケージも対応可 - サービスの特長:
- 購入前の現地車両調査レポート提供
- 通関・登録・排ガス検査・名義変更まで一貫サポート
- 欧州車・イギリス車に特化した並行輸入業者。クラシックカーの扱いにも実績あり
- 料金体系:
- 代行手数料:20万円~50万円程度(条件に応じて)
- 輸送費・保険:実費請求
- 車検・改善整備オプション:5万~15万円追加 - サービスの特長:
- 関税・消費税すべて込みの「総額表示」スタイルが安心
- 希望車種を伝えると車探しからスタートしてくれる
- 「関税・消費税込みかどうか」「登録・車検費用までカバーされているか」
- 「対応スピード・レビュー評価」「メールや電話でのやりとりの丁寧さ」
- 「保証やアフターサービスの有無」などをしっかり比較しましょう。
ここまでのまとめ
- 自力輸入は確かに安いが、手間・知識・リスクも大きい
- 業者依頼は割高でも、トラブル回避・時短・安心感が魅力
- 自分の「予算・時間・経験値」によって、どちらを選ぶかが変わる
- 信頼できる業者を選べば、費用以上の満足度が得られる可能性も大
関税申告のために必要な書類一覧と書き方のポイント

輸入車の通関・関税申告では・・・
必要な書類の不備や記載ミスが
トラブルの原因になることが非常に多いです。
港に車が到着しても、書類に不備があると
通関ができず、保管料が発生したり、
輸入そのものが遅延してしまうことも。
そこでこの章では・・・
関税申告に必要な書類と、具体的な書き方・注意点を
分かりやすく解説します。
これを読んでおけば・・・
初めての方でも安心して通関手続きが進められるはずです。
Invoice・B/L・車両登録書の記載例と注意点
まず、関税申告において必須となる
基本書類は以下の3点です。
インボイス(INVOICE/商業送り状)
輸出者(販売元)が発行する請求書で、
車両の価格・通貨・輸出国・買主などが記載されています。
- 販売者名・住所
- 購入者(あなた)の氏名・住所
- 車両の詳細(メーカー・モデル・年式・VINナンバー)
- 単価・合計金額(通貨明記:USD、EURなど)
- 貿易条件(CIF/FOBなど)
- CIF(Cost, Insurance, Freight)価格が明記されていないと、税関側で推定されてしまい、余計な税金を払うことになる可能性あり。
- 手書きやPDFスキャンの場合も可ですが、改ざんや不明瞭な記述はNG。発行元の署名・社印があると安心です。
B/L(Bill of Lading/船荷証券)
輸送業者(シッピングカンパニー)が発行する、
貨物の輸送証明書です。
車両の引き取りに必要になります。
- 発送地・到着地(例:Los Angeles → Yokohama)
- 輸送業者名
- コンテナ番号・シリアル番号
- 車両情報(VINなど)
- Consignee(受取人):通常はあなたの名前
- B/Lが「Original(原本)」でないと通関できないこともあるので、輸送業者に電子B/Lではなく紙のオリジナルを送ってもらうように指示しておくと安心です。
- 車両が複数台ある場合は、それぞれにVIN(車体番号)記載が必要。
車両登録書(Title/Registration)
中古車の場合、現地での所有者登録証が必要です。
アメリカなら「Title」、イギリスでは「V5C」などと呼ばれます。
- 車両の所有者が明確であること(転売・盗難車でない証明)
- VINナンバーと年式・車種が一致しているか確認
- 売買日や譲渡証明(Bill of Sale)があるとベター
- 書類の所有者とインボイスの売主が一致しないと、偽装取引や二重売買と疑われるリスクあり。
- 登録書の原本、またはコピーに署名・スタンプがあるか確認しましょう。
税関申告書の具体的な書き方と提出方法
関税申告にあたって提出する最終書類が、
「輸入申告書(Form C-5020)」などと呼ばれる
税関提出用の申告書です。
これは通関業者に任せるケースが多いですが、
自力で輸入する場合は自分で記入・提出する必要があります。
基本的な記載内容
| 項目名 | 内容の記入例 |
| 輸入者名 | 山田 太郎(Yamada Taro) |
| 住所 | 東京都港区〇〇… |
| 品名 | 自動車(Automobile) |
| 数量 | 1台 |
| 原産国 | アメリカ合衆国(USA) |
| 輸出港 | ロサンゼルス港(Port of L.A.) |
| 到着港 | 横浜港(Yokohama) |
| CIF価格 | ¥3,375,000 |
| 関税率 | 10%(または免税条件を記載) |
| 支払方法 | 銀行振込、または現金 |
提出方法
- 税関窓口に直接持参
- または、通関業者に依頼して電子申告(NACCSシステム)で送信
- 提出時にはすべての添付書類(インボイス・B/L・登録書など)をセットで準備
ミスが起こりやすいポイント
- 「CIF価格」と「FOB価格(本体価格のみ)」を混同して申告 → 課税額が変わる
- 輸出港と到着港の記載ミス → 通関がスムーズに進まない
- 年式や車種の入力ミス → 関税率が変わる可能性もあり
ここまでのまとめ
- インボイス・B/L・登録証の3点セットは必須書類
- 記載ミスや不備があると、通関ストップ・追徴課税・延滞金のリスクも
- 書類は「正確・明瞭・原本」を意識し、不安な方は通関業者への相談がベスト
車を日本に持ち込んだ後の登録・ナンバー取得の流れ

海外から無事に車を輸入できたとしても、
それで終わりではありません。
日本で公道を走らせるためには
「登録(ナンバー取得)」という
最後の関門が待っています。
特に並行輸入車の場合・・・
日本の基準に適合しているかどうかを証明する
「自動車検査(車検)」を受けなければならず、
思っていた以上に手間と時間がかかることもあります。
この章では・・・
車を日本に持ち込んだあとの具体的な登録・
検査の流れを、実際の所要時間や必要書類とともに
詳しく解説します。
陸運局での手続き、必要な書類と所要時間
ナンバーを取得するためには、
最寄りの運輸支局(陸運局)で
登録手続きを行う必要があります。
ここで登録を済ませないと、車検にも進めませんし、
公道を走らせることはできません。
登録に必要な主な書類一覧(普通車の場合)
| 書類名 | 内容・備考 |
| 輸入車届出書(型式指定のない車用) | 並行輸入車は原則これが必要 |
| 通関証明書(税関発行) | 関税・消費税の支払いが完了した証明 |
| 車両の諸元表 | 車のサイズ・重量・排気量など技術情報 |
| 所有者の住民票 or 登記簿謄本 | 個人・法人で異なる |
| 印鑑証明書/委任状 | 登録手続きを他人が代行する場合も必要 |
| 自賠責保険証明書 | 新規で37ヶ月分を用意(登録月による) |
| 車庫証明(普通車のみ) | 事前に警察署で取得が必要 |
| 予備検査証(後述) | 技術基準適合を証明する検査結果 |
所要時間の目安
- 書類がすべて揃っていても、登録当日は最低でも半日~1日がかりになることが多いです。
- 書類の不備や補足が必要な場合は、再訪問や再提出も覚悟しておいた方がいいでしょう。
ドイツから輸入したフォルクスワーゲン・ゴルフを個人で登録する場合、
「通関証明書」「予備検査証」「車庫証明」「印鑑証明書」などを持参し、
陸運局で手数料印紙(約2,000円)を購入し、手続きカウンターに提出 → 登録完了後、ナンバープレートが発行されます。
自動車検査(車検)で注意すべき技術基準とは?
並行輸入車で最も時間と費用がかかるのが、
車検(自動車検査)における“技術基準の適合性”
チェックです。
日本の車検でチェックされる主なポイント
| チェック項目 | 輸入車でありがちな問題 |
| 灯火類(ヘッドライト・ウィンカー) | 左右の光軸/色・明るさが基準外のことも |
| スピードメーター | マイル表示→キロ表示への変更が必要 |
| 排気ガス規制 | 年式・排気量に応じて「排ガス試験」が必要になる場合あり |
| 騒音規制 | マフラー音量オーバーで不合格になることも |
| サイドミラー・バックミラー | 海外仕様が日本基準外で再設置が必要 |
アメリカから輸入したシボレー・カマロ(左ハンドル)を登録する場合・・・
- ヘッドライトのカットラインが右側通行仕様 → 国内用に交換(約5万~10万円)
- スピードメーターがマイル表示 → メーター交換または変換ステッカー装着
- 排ガス試験で基準オーバー → 排気系パーツ交換やECU書き換えが必要に(数万円~数十万円)
検査の種類と費用目安
| 検査の種類 | 費用の目安 |
| 予備検査(構造・技術確認) | 約15,000円~30,000円 |
| 排ガス試験・騒音試験 | 1項目あたり2万~5万円前後 |
| 必要に応じた整備・改修費 | 数万円~15万円以上かかることも |
- 輸入前に「日本の基準に近い車種」を選ぶ(右ハンドル仕様やEU圏モデルなど)
- 輸入代行業者に「予備検査込み」で依頼することで、最初から整備された状態で納車されることも多いです
ここまでのまとめ
- 登録には「通関証明書・予備検査証・車庫証明」など多数の書類が必要
- 手続きは半日~1日がかり、事前準備で時短できる
- 技術基準適合のために、整備費用が別途数万円~十数万円かかるケースもある
- 初めての方は、予備検査・登録まで含めたフルサポート業者の利用も検討の価値あり
中古車輸入でかかる「隠れコスト」排ガス規制・車検対応の費用

中古車の輸入は、新車に比べて車両価格が安く、
希少なモデルも手に入りやすいというメリットがあります。
ですがその一方で・・・
日本国内での登録や車検を通すために
想定外の「隠れコスト」が発生するケースも
少なくありません。
特に気をつけたいのが・・・
「排出ガス規制」や「日本の保安基準への適合」
といった技術面での対応です。
ここでは・・・
実際にどのような費用や手間がかかるのかを、
具体的な例とともに詳しくご紹介します。
排出ガス試験・騒音検査の費用と手間
中古車を輸入する際・・・
排出ガス(排ガス)試験や騒音検査は、
日本の環境基準を満たしているかどうかを
チェックする重要な検査です。
特に年式の古い車や、大排気量エンジンを
搭載している車はこの部分で苦戦することが多く、
登録の大きなハードルになりがちです。
排出ガス試験(JATA・JARIなどの公的機関で実施)
- アイドリング中・加速時のCO、HC、NOxの排出量測定
- 年式・排気量ごとの基準に適合しているかを判定
- 1回あたり 4万~7万円前後(車種・試験内容によって異なる)
- 再試験になった場合は追加費用が発生
2005年式のアメリカ仕様フォード・エクスプローラー(V6 4.0L)を輸入した場合、排ガス基準に適合しない可能性が高く、排気系部品の交換やコンピュータ(ECU)の調整が必要になることがあります。
騒音検査(加速騒音/定常走行騒音)
- 車両を加速・走行させたときの騒音レベルを測定
- 日本の道路交通法で定められた上限値を超えていないかをチェック
- 1回あたり約2万~4万円程度
- マフラー音が基準超過の場合は、消音器交換(社外マフラー→純正化)が必要になることも
- 排ガス・騒音ともに検査は1台ずつ個別対応になるため、時間がかかります
- 試験スケジュールの都合で、予約から受験まで1~2週間待ちになることも珍しくありません
日本の保安基準を満たすための改修コスト
輸入車は、そのままの状態では・・・
日本の保安基準に適合していないことも多く、
登録前にさまざまな改修が必要になるケースがあります。
これが“隠れコスト”として後から、
のしかかってくるポイントです。
代表的な改修項目と費用の目安
| 改修項目 | 内容 | 費用の目安 |
| ヘッドライト交換 | 左右通行の違いで光軸がズレる(北米仕様→日本仕様) | 5万~10万円 |
| スピードメーター変更 | マイル表示→キロ表示(ステッカー or メーター交換) | 1万~5万円 |
| ウィンカー/テールランプの色変更 | 北米仕様は赤ウィンカーが多く日本ではNG | 1万~3万円 |
| サイドミラーの形状変更 | 角度・サイズが基準を満たしていない場合あり | 2万~4万円 |
| 速度警告音装置の装着 | 日本では一定速度以上で警告音が必要(新車扱い時) | 5,000~1万円 |
| リアフォグランプ追加(EU車) | 装備されていない車も多い | 5,000~1万円 |
| マフラー交換 | 騒音基準オーバー時に必要 | 3万~10万円以上 |
イギリスから並行輸入したランドローバー・ディフェンダー(2003年式)は・・・
- 左通行対応のヘッドライトに交換(7万円)
- マフラーが音量基準をオーバーし、社外品から純正に交換(9万円)
- テールランプを日本仕様に交換(2万円)
合計で約18万円の改修費がかかりました。
- できるだけ「右ハンドル・日本仕様に近いモデル」を選ぶ
- 輸入代行業者に「車検適合整備込み」のパッケージを依頼する
→ 整備費用を最初から見積もりに含められるため、後からの出費が減ります。
ここまでのまとめ
- 排ガス・騒音検査は1回数万円+再試験の可能性あり
- 技術基準を満たすための改修費は車種によって大きく異なるが、数万円~20万円以上になることも
- 事前に基準適合性を調べる or 業者に相談することで、トータルコストを抑えられる
この記事のまとめ

輸入車の関税は・・・
購入方法や国、車種によって
大きく異なります。
特に「誰が関税を払うのか?」という疑問は、
個人輸入か業者依頼かで流れが変わります。
今回の記事では・・・
- 関税の支払い義務や「関税込み表示」の落とし穴
- 国別の関税率やEPA協定による免税条件
- CIF価格をベースにした課税方法とその内訳
- 排ガス試験・技術基準への対応などの“隠れコスト”
- 自力輸入と業者依頼の費用・手間・リスク比較
といったポイントを詳しく解説しました。
これから輸入車を検討される方は・・・
ぜひ参考にして総額での判断を心がけてみてくださいね。
ここまで、長かったかと思われますが、
最後まで目を通していただき、
ありがとうございました。

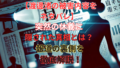
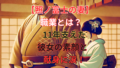
コメント